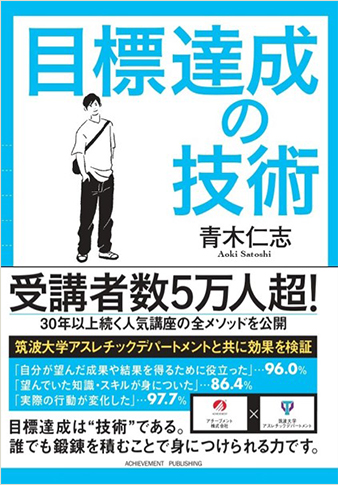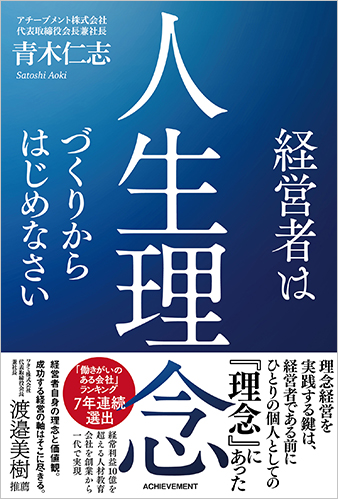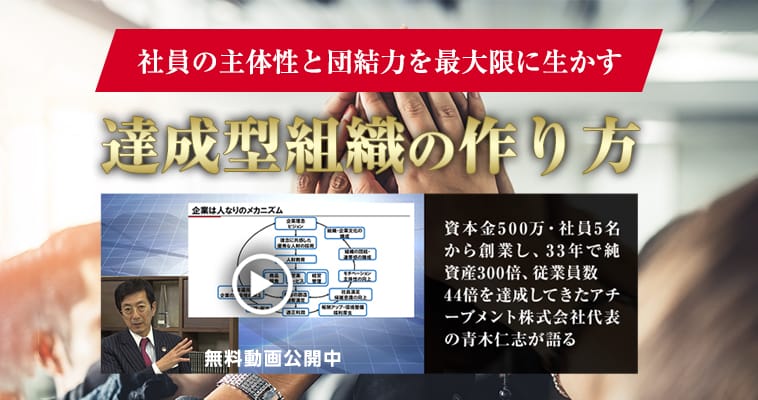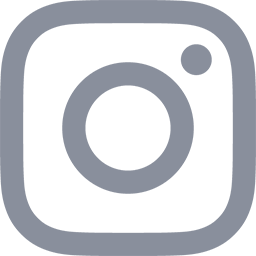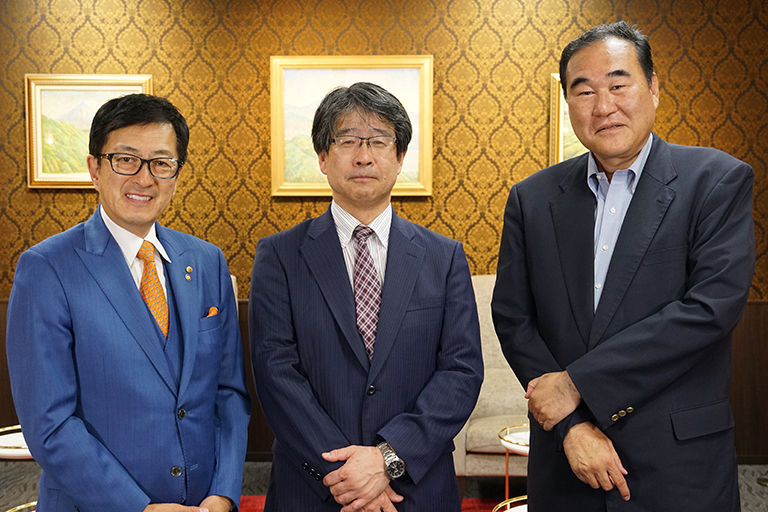
-
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 委員長
中村 洋氏
-
アチーブメント株式会社 顧問 木俣 佳丈氏
- アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長
青木仁志
地図なき時代を乗り切るための、
リーダーシップと人材育成を考える
世界が急速に変化し、政治・経済とも予測困難な情勢が続くなか、多くの企業、そしてビジネスパーソンは難しい対応を迫られている。そうした困難な時代を切り拓くために、企業経営者は組織をどのように先導すべきなのか。そして次代のリーダーをいかにして育成していけば良いのか──。日本初のMBAを開設したビジネス・スクールとして、世界一線級の研究を発信し続けてきた慶應義塾大学ビジネス・スクール(KBS)。同学の研究科委員長として組織を牽引する中村教授を招いてお話を伺った。
先見性を高めるために視野を広げ、視座を高める
 木俣
木俣本日はKBSの研究科委員長である中村先生にお越しいただきました。同学は1962年に創立された日本で最も歴史のあるビジネス・スクールで、1978年には日本初のMBAを開設。その後、専門研究者を養成する博士課程、より高いレベルの経営スキルを探究するExecutive MBA(EMBA)プログラムなどを開設し、経済界に数多くの人材を送り出しています。

KBSのミッションは、「新たな構想をつくって実現するリーダーを育成すること」です。実務経験と体系的な知見を融合する場を提供しています。

まさに日本のビジネス界をリードする人材の育成に、寄与されているお立場ですね。本日は貴重なお話が伺えるものと期待しています。
 木俣
木俣まずは今日の日本のビジネス界や、民間企業の状況について伺いたいと思います。昨今の日本企業を一望すると、キラリと光る会社は散見されるものの、全体として「勢い」を感じにくい状況にあると思えてなりません。

グローバル化の加速、情報技術の伸展とAIの普及、人口構成の変化、新興国の成長…。そういった様々な変化に直面し、ビジネス環境の複雑性、不確実性が増しており、いま多くの企業が難しい状況に直面しています。実際、かつては世界を席巻した日本の基幹産業を担う大手企業が難局を迎え、それに連なる中小企業が苦境に追い込まれるという状況も見受けられます。確かに「勢い」を感じにくい状況かもしれません。ですが先ほどおっしゃったとおり、日本にはキラリと光る企業が数多くあります。中小企業が有するテクノロジーやサービスに関しても、発展性を秘めたものがたくさんあると感じています。

そうした可能性をもつ企業、特に中小企業が新たな成長を目指すために、必要なことは何だと思われますか。

中小企業がもつ独自のテクノロジーやサービスのなかには、自社内で考えている以上に潜在力を有するものがあるものです。仮に従来の市場で成長が鈍化していたとしても、意外な市場でニーズが見込まれる可能性もあります。また国内向けの商品やサービスを海外に発信するなど、発想の転換によって新たな販路が広がることもあります。
 木俣
木俣自社の技術やサービス、資産などを、これまでとは異なる視点から見直すことが大事だということですね。

そのためにもリーダーが「視野」を広げるとともに、「視座」を高める努力が必要です。そうした目で世の中の潮流を見極めることで、自社の強みを活かすための新しい道筋が見えてきます。

38年、人材教育に従事し9000名以上の経営者の方に触れてきましたが、改めて思うのは、経営者の器以上のビジネスは生まれないということです。リーダー自身が学び、自分を成長させ続けることが大切ですね。
 木俣
木俣そのとおりですね。世界ではスティーブ・ジョブズやスンダー・ピチャイ、イーロン・マスクなど、シンボリックな経営者が次々と世に出ています。日本にもかつては松下幸之助さんや本田宗一郎さんのような、卓越した人物がいました。もちろんいまも優秀な経営者はいますが、業界を超えて尊敬され、世界に影響を与えるようなリーダーが、さらに出てくることを期待しています。

本田宗一郎さんといえば、彼は「リーダーシップとは、その目標をはっきりと見せること」だと語っています。これはとても大事なことで、リーダーには先々を見通す能力が必要です。5年10年先の社会を読み、自社の目標を定めて社員を導く。それができる人が真のリーダーではないでしょうか。例えばホンダ社でいうと、低公害エンジンCVCCの開発が好例です。米国では1970年にマスキー法という厳しい排出ガス規制が制定されましたが、CVCCはこの規制をクリアした最初のエンジンとして注目されましたね。それは本田宗一郎さんが、「今後は環境問題が重視されるようになる」という世の中の流れを見極め、社員を鼓舞し、技術開発へ存分に力を注いだからこそ実現できたのだと思います。
 木俣
木俣CVCCを開発した当時、ホンダの自動車生産量はゼネラルモーターズの五十分の一、トータルな規模は三百分の一とも言われています。その他フォードやクライスラーなどの3大自動車メーカーが席捲している市場に立ち向かっていくのは無謀な挑戦とも思えます。ですがそこには先々を見通す眼力と、「まだ世の中にないものを創りたい」という熱い思いがあったのでしょう。

同感です。松下幸之助さんも先々を見据え、社会の求めに応じて努力することの重要性を説きました。社会のニーズを先見できる経営者が、自社を大きく成長させられるということですね。そのためにも先ほど中村先生がおっしゃったように、学びによって視野を広げ、視座を高めることは肝要ですね。

ケースメソッドで「考える」力を錬磨し、現場で活きる経営学を修得

日本初のMBAを開設したKBSは、まさに世界最高峰のビジネス・スクールだと私は思っています。ビジネスの最前線で活躍する人材を育成するために、御校が工夫されているのはどんなことでしょうか。

まず基本的な学習スタイルとしては、ケースメソッドを中心とした実践的な教育を行っていることが大きな特色です。実際の企業や組織が直面した経営課題を取り上げ、テキストを事前に読み込んだうえで各受講生が分析結果や、意思決定の内容とその理由などを発表し、討論を重ねます。教員が受講生に対して一方的に教えるというようなスタイルはとっていません。実践的な経営能力を身につけるためには、双方向型の授業方法が極めて有効なのです。また指導においては、受講生が自ら「考える」ことを最重視しています。

経営者の立場になり、自分ごととして真剣に考える。それを習慣化することで、「現場で活きる経営学」が身につくのですね。

はい。考えてディスカッションし、また熟考する。その繰り返しによって思考を深めていきます。様々な業種の第一線で活躍されているビジネスパーソン同士で議論し合い、要所で教員が突っ込んだり、新たな視点を提示したりというトレーニングはとても有効で、思考力を大いに研磨できます。海外拠点のマネジメントや新領域の事業への取り組み、MBOなど、これまで経験のない業務に取り組むことになった際には、新たなスキルが求められますね。そうしたときに過去の職務に限定された経験や、社内のOJTだけで対応することは困難でしょう。経営を専門的に学び、実践的なスキルを身につける必要性は増しているのです。
 木俣
木俣ビジネス環境が激しく変化・複雑化するなか、ビジネス・スクールが果たすべき役割はますます重要になると思います。冒頭でもお話ししましたが、いまの日本経済から「勢い」が生じにくいと感じられるのはなぜなのでしょう。

まず大きな流れでいうと、日本経済に勢いがあった1950~60年代は、人口が右肩上がりで労働力人口が増え続けていて、人々の購買意欲も高い時代でした。また事業を成長させるためのお手本が、海外企業の例を始めとして豊富にあったんですね。そのため企業を成長させるための道筋が見えやすく、その路線に沿って猪突猛進すれば良いというのが高度成長の時代でした。しかしいまは、少子化率でも高齢化率においても世界最高レベルの水準にあり、労働力人口が減り続けています。またある程度生産性も高まり、次にすべきことを示してくれる教科書がありません。目指す方向が定まりにくく、正解を手探りしながら歩んでいるような状況なので、「勢い」を感じにくいのでしょう。しかしこうした時代だからこそ、自分自身で「考える」能力が肝要になってくるのです。

地図がない原野を、知恵だけを頼りに歩いているような状況ですね。社員を先導する経営者としては、まさに心血を注いで、進むべき道を考え抜く覚悟が必要だと思います。実は、私は事業創造大学院大学という大学院で客員教授をしています。私自身38年間にわたってアチーブメント社を成長させ、6万人以上の方に目標達成プログラムを伝えてきましたが、そうした事業で得たビジネス上の知見に対する学術的な裏づけを、MBAで得られると感じています。先人が築きあげてきた経営に関する知と経験の集大成を学び、研究できるMBAは大いに価値があります。
志と地域愛そして危機意識が、ビジネスの新たな沃野を拓く
 木俣
木俣いまは手本なき困難な時世だというお話が先ほど出ました。そうしたなか、新しい時代の胎動を感じられるような事業というものはありますか。

日本の潜在力はとても大きく、興味深い取り組みは多々ありますが、私の主要な研究領域である医療・介護分野で気になった取り組みについてお話ししたいと思います。一つは山形県の「日本海ヘルスケアネット」という取り組みです。少子高齢化、過疎化が急速に進むなかで、地域の将来の医療需要に対応できるよう医療法人の間で業務の連携を進めるとともに、「地域フォーミュラリー」という医薬品の使用指針を日本で初めて導入し、適正使用を推進するとともに、薬剤費の適正化を図っています。また、地域の住民が、適切な医療、介護、福祉、生活支援を切れ目なく受けることができる取り組みを進めています。

病院経営の困難さが取りざたされ、地域医療の危機が懸念されるなか、医療の効率化と質の向上につながる素晴らしい取り組みですね。

はい。また他県の事例ですが、高齢者総合ケア施設でのユニークな試みもあります。高齢者施設というと、住宅地から遠く離れた場所に設置されることが多いのですが、そうではなく暮らし慣れた地域社会のなかに施設を設置し、高齢者と介護者の負担、地域社会の負担を減らしながら、その人らしい暮らしを支えようという取り組みです。その事業では利用者の方が住み慣れた地域に「小規模多機能」な施設を複数設け、介護の様々な機能をもつ各拠点が連携。物流の効率化を図ったり、職員が情報共有したりすることで、入居者へのサービスの質を高めています。また職員同士が密にコミュニケーションをとることで、業務が円滑に進むようになって人間関係も良くなり、介護の現場で問題視されている離職率も減りました。「小規模多機能」というと非効率的だと思われがちですが、ここではとても効率的な仕組みになっている。これはいわばコンビニストアのビジネスモデルに近いといえるでしょう。
 木俣
木俣なるほど。どちらの例も地域や社会が抱える問題に対応した試みですね。

はい。着目すべきは、そうした新しいビジネスモデルが、地方から生じていることです。その理由としては、地方は高齢化や地域医療の問題が顕在化しやすく、危機意識がより強いということが挙げられます。そしてもう一つのポイントは、都市部よりも「スモールスタート」がしやすいということ。大きな組織の場合、物事を進める際に反対者や傍観者が出やすくなります。ですが同じ危機意識や地域への思いを共有する仲間が事業を小さく始めることで、成果が出やすい組織がつくれるのです。

とても示唆に富むお話です。地域愛と切迫した危機意識。そして思いを共有できるチームがあったからこそ、苦境のなかで新たなビジネスモデルを創造できたのですね。「あらゆる逆境には、同等かそれ以上の成功の種が隠されている」と私は常々思っていますが、その好例だと感じます。私はこれまで様々な経営者を見てきましたが、経済的な豊かさを得ることが目的化して、新たなビジネスモデルをつくってすぐにバイアウトするような経営者も多くいます。いま中村先生が話された例はそうではなく、社会貢献に対する志がありますね。そのように本質的な価値を追求する姿勢で、ビジネスに臨むことが大切だと思います。
 木俣
木俣本日は貴重なお話を伺えました。ありがとうございます。
中村 洋(なかむら ひろし)
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 委員長 慶應義塾大学ビジネス・スクール 校長
1988年、一橋大学経済学部卒業。1996年にスタンフォード大学博士課程修了(Ph.D.取得)後、慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師に就任。同大学院助教授を経て2005年に教授に就任。現在は慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長を務める。厚生労働省中央社会保険医療協議会公益委員。主な研究領域は、ライフサイエンス産業、経営・組織戦略、ヘルスケアにおける連携 他。2006年に医療経済賞受賞。